敷き詰めたヒートシンクを冷やせる新型ファン搭載で性能も向上したSteel Legend
編集部:ありがとうございます。では、Steel Legendに関してはいかがでしょうか?

原口氏:Steel Legendは元々迷彩柄だったのですが、昨今の世界情勢を鑑みまして、より機械的なデザインに変更しています。特徴としては名前のとおりで、高耐久・高品質な部材をふんだんに使っています。
具体的に言うと、平たくて四角いSPコンデンサと呼ばれる固体コンデンサを使用しています。日本メーカーの、そのコンデンサを使うことで、抵抗値を下げることができます。

原口氏:低ESR(Equivalent Series Resistance)と呼ばれるものになるのですが、通常のメーカーさんだと6Ω(オーム)だったり、ちょっと良い製品だと4.5Ωだったりします。しかし、Steel Legendでは3Ωのものを使っています。
それにより、抵抗値を下げることができ、その結果発熱を下げれています。その結果、より効率良く消費電力を使用し、ブーストクロックの伸び率が良くなっているのです。
編集部:なるほど。性能面に関わる他のパーツの特徴はありますか?
原口氏:ヒートパイプもぎゅうぎゅうに敷き詰めています。ASRockの見解ではダイレクトヒートパイプはあまり冷えません。そのため、銅のコンタクトエリアを用意し、一度受動プレートでしっかりと吸熱した後、ふんだんに使ったヒートパイプで各フィンに上手く熱を伝えるようにしています。
また、フィンの密度も詰まっています。一般的なメーカーさんだと、1.75mmや2mm近いメーカーさんも昔はありましたが、ASRockの製品は1.5mmや1mmといった間隔で敷き詰めています。

編集部:それにはどういったメリットがあるのですか?
原口氏:メリットは表面積が稼げるため排熱効率が上がる可能性があります。ただし、静圧が高いファンを使わなければ、風が抜けてくれないので、熱が溜まってしまうというデメリットもあります。
Steel Legendでは、外周が全て繋がっているリング状のファンである「Striped Ring Fan」を採用し、静圧が高くなったことで、実測値で最大GPUの温度が6度下げられるようになりました。
元々「Striped Ring Fan」は、ハイエンドなビデオカードにしか採用していなかったのですが、今回のSteel Legendはサイズを変更し、90mmのファンを採用できました。
編集部:その結果、高い性能が出せるということでしょうか。
原口氏:そうですね、そうした高品質で高耐久な部材を使ているお陰なのか、ファレンスよりもGPUクロックが大体200MHzぐらい高くなっています。
編集部:今回Phantom Gamingのモデルが出ていませんが、Steel Legendが十分高いゲーム性能を発揮してくれるんですね。
黒くファンも光らないSteel Legendは海外需要から生まれた!?
原口氏:海外では、Steel Legendの高耐久シリーズのビデオカードが欲しいという要望が結構あったようで、Steel Legendというと白基調のビデオカードが多いんですが、色違いでSteel Legend Darkという黒いモデルも発売しました。
違いはカラーが黒くなり、ファンが光らなくなった、という2点です。

編集部:ファンを光らさなかった理由は?
原口氏:黒いビデオカードでファンを光らせると、(光りに)黒色が入ってしまうので、自分の出したい色に調整するのが難しくなるので、LEDは搭載しませんでした。
編集部:ちなみに今回Phantom Gamingでは製品を出さないのでしょうか?
原口氏:マザーボードだったら、ゲーミング要素を持っているUSBポートだったり、専用機能が付いていたりしていますが、ビデオカードの場合はそうしてゲーミング要素の機能が付いていないのに“ゲーミング”って名乗ってよいのか、という社内的な葛藤もあり、今回は出すのをやめています。
編集部:ソフトウェアで、何か機能を付けてという考えはないのでしょうか?
原口氏:我々の中ではハードウェアが持っている機能ではないと、という想いもありますし、オーバークロックを推すと別にTaichiというブランドがあるので、コンセプトがズレるのかなと。Phantom Gamingだったら、例えば内蔵でキャプチャーデバイスが最初から付いていて、ゲームが配信できますとか。SSDが取り付けられますとか、そういった方向の面白さがあっても良いんじゃないかとは思っています。
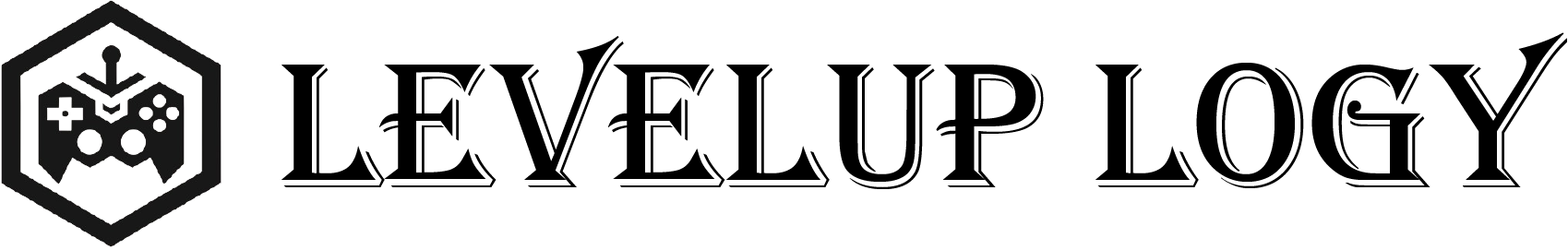







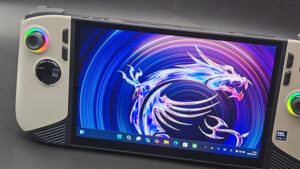







コメント