文●藤田忠 編集●ハッチ

手の平サイズでCore Ultra 9を搭載した最新NUC
NUC(Next Unit of Computing)は、インテルが2012年に発表し、2013年に市場に投入した1辺が約10cm(4インチ)となるUCFF(Ultra Compact Form Factor)フォームファクターを採用したベアボーンキットだ。省スペースで使える小型サイズながら、ビジネスワークや写真の編集・管理、動画視聴など、普段使いにも使えて一定の人気を誇っていた。
しかしながら、2023年インテルはNUC事業への直接投資からは撤退すると発表し、ASUSが事業を引き継いだ。そして、2024年5月に新製品発表会を実施し、多数のラインアップを発表した。NUCにはCPUを搭載するが、メモリやストレージを内蔵せず、別途購入して自分で組みこむベアボーンキットと、最初からメモリとストレージも取り付けられている完成品のMini PCがある。
ASUSのNUCもシリーズごとにベアボーンキットや完成品のMini PCがラインアップにある。今回ピックアップした上位モデルの「NUC 14 Pro+」もCPUが3種類で、ベアボーンキットとMini PCのどちらのモデルも用意されている。しかし、一般にはベアボーンキットのみが販売されていて、Mini PCは法人のみの販売となっている。
ASUSからは、テスト機としてCore Ultra 9 185Hを搭載した「型番:NUC14RVSU9」をベースとし、1TB SSD、32GBメモリを備えた「NUC 14 Pro+」をお借りした。搭載するメモリによっては、多少性能結果が変わってくるが、本製品がどういった製品で、どれぐらいのパフォーマンスを発揮するのかを、確認してご紹介したい。
アルミニウムシャーシが特徴の美しいデザイン
1つ下のモデルである「NUC 14 Pro」は黒を基調としているが、その上位モデルの「NUC 14 Pro+」は、5×4インチのアルミニウムシャーシを採用し、デザインから異なる。より高級感があり、見た目にもスタイリッシュな印象だ。


CPUはCore Ultra 7 155H/165H搭載モデルもあり、そのCPUによってACアダプターの容量が異なる。また、標準でVESAマウントが付属していた。


2基のUSB4.0やHDMI出力端子とインターフェースは充実だ
コンパクトながらCore Ultra 9 185Hと高性能なCPUを搭載する「NUC 14 Pro+」は、使い勝手に影響するインターフェースも抜かりなしだ。有線LANは未だ1Gbpsが多いなか、より高速な2.5G LANを搭載し、無線LANも6GHz帯が利用できるWi-Fi 6Eを備える。
そして最も気になるUSBポートは、前面に転送速度20GbpsのUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1基、10GbpsのUSB 3.2 Gen 2×2基を搭載する。さらに背面には最大40Gbpsの転送速度を実現するUSB4/Thunderbolt 4×2基、USB 3.2 Gen 2×1基、USB 2.0 Type-A×1基など、小型ながら十分な数を備えている。





残念ながら、USB4/Thunderbolt 4ポートはUSB Power Delivery(USB PD)には非対応だが、DisplayPort Alternate Modeの映像出力に対応する。2基のHDMI端子と合わせて、4画面までの出力が可能だ。さらに、40Gbpsの高速転送を活用したUSB4/Thunderbolt 4対応NVMe M.2エンクロージャーによるストレージの増設や10G LANの追加など、小型PCでどうしても弱くなる拡張面をカバーしている。

32GBメモリ、1TB SSD搭載モデルで検証
「NUC 14 Pro+」シリーズは、ベアボーンキット、小型PCともに16コア/22スレッドとなる高パフォーマンスCore UltraプロセッサーのCore Ultra 7 155H/165Hに、Core Ultra 9 185Hの3種類が用意されている。
しかし今回は、冒頭で述べたようにPコアの最大ブーストクロックが5.1GHz、Eコアが最大3.8GHz、LP Eコアが最大2.5GHzで動作するCore Ultra 9 185Hを搭載する「NUC14RVSU9」をベースに1TB PCIe4.0×4 NVMe SSD、DDR5-5600 32GBメモリを搭載したモデルで性能を検証してみた。






CPU性能はRyzen 7 7800X3Dにも迫る性能!
まずは3DCG作成アプリ「Cinema 4D」のレンダリングエンジンを用いてCPUの処理能力を計測する定番ベンチマーク「CINEBENCH」を実行した。CINEBENCHの最新バージョンとなる「CINEBENCH 2024」に加え、これまでの計測データが豊富な「CINEBENCH R23」でも計測した。


モバイルCPUの中では最上位であるCore Ultra 9だけあってCINEBENCH 2024のマルチコアは、1000ptsには届かなかったものの約900ptsを記録した。また、CINEBENCH R23はマルチコアで17000ptsと高い。
さすがに消費電力盛々のデスクトップCPUのインテル第14世代Coreプロセッサには届かないが、第12世代Core i5や、AMD Ryzenの6コア/12スレッドCPUの「Ryzen 5 7600」や、ゲームに特化したCPUの「Ryzen 7 7800X3D」に迫るスコアとなっている。
続いて総合ベンチマークソフトのUL Solutions「PCMark 10」を計測した。

結果は総合スコアが7651ポイントとなかなか優秀だ。テストごとのスコアを確認すると、ビデオ会議などの日常使いに関する「Essentials」、オフィス処理の「Productivity」、写真や動画などのクリエイティブに関わる「Digital Content Creation」のいずれのテストでも、PCMark 10が定める推奨スコアの2倍以上となる10000ポイント超えと文句なしのスコアだ。
PCMark 10のテストは、若干古くなりつつあるが、日常使いから、オフィスアプリ、レポートなどに貼り付ける写真の編集など、Mini PCで行いたいことを、スムーズに行うことができるだろう。
オフィス処理などのスコアはデスクトップ向けCPU並み!
次は「Microsoft Office(Microsoft 365)」や、「Adobe Photoshop」、「Adobe Lightroom Classic」、「Adobe Premiere Pro」で実際に処理を行い、そのパフォーマンスを測る「UL Procyon」を実行していこう。

まず「Office Productivity Benchmark」を実行すると、総合スコアが6424ポインを記録。アプリごとのスコアもWordが8313、Excelが6259、PowerPointが6881ポイントを記録している。比較的処理に時間のかかるPDFファイルの出力もスムーズに行えている。ストレスを感じることなく、「Microsoft Office(Microsoft 365)」を使えるだろう。
次は「Adobe Photoshop」、「Adobe Lightroom Classic」のパフォーマンスをチェックする「Photo Editing Benchmark」のスコアを確認しよう。

結果は総合スコア5620、Adobe Photoshopを使用し、CPUとGPUを使って処理される「Image Retouching」が7203。Adobe Lightroom Classicを使用し、おもにCPUで処理される「Batch Processing」のスコアが4383となっている。
これはCINEBENCH系と同じく、デスクトップ向けAMD Ryzen CPUのメインストリームとなるRyzen 5 7600(iGPU使用)の結果とほぼ並んでいる。実際、テストでは実際にさまざまな作業が行われるが、スムーズに処理されていた。スマホやデジカメで撮影した写真のRAW現像や編集、管理を快適に楽しめるだろう。
続いて「Adobe Premiere Pro」を使用する「Video Editing Benchmark」のスコアを確認したい。

iGPUのIntel Arc Graphicsを処理使用してテストすると、スコアは8812ポイントとCPUのみで処理を行った際の倍近いスコアを記録した。スコアだけでなく、動画の処理に要した時間も大幅に短縮し、H.264で100秒台、H.265で200秒台を記録している。iGPUを使ったモバイル向けプロセッサとしては十分な処理能力と言えるだろう。
『鳴潮』も遊べる高いゲーミング性能も有する
最後に、Intel Arc Graphicsのゲーミングパフォーマンスを定番ベンチマークの「3DMark」で確認していこう。
まず「3DMark」の最新のDirectX 12ベースベンチマークプリセット「Steel Nomad」の軽量版となる「Steel Nomad Light」を実行した。

軽量向けベンチマークとは言え、解像度はWQHDとあってスコアは3000台と低めで、テスト中のフレームレートも22FPSと、ゲームプレイのボーダーラインとなる30fpsを切っている。新世代ベンチマーク&高解像度だけあるので、この結果はやむを得ないだろう。
続けて、Windows PCおよびAndroid端末向けのゲーミングテストで、Vulkan 1.1 APIとGPUでのハードウェアレイトレーシング機能を利用した新世代テストとなる「Solar Bay」のスコアを確認しよう。

スコアは高くはないが、テスト中のフレームレートはゲームを楽しめる30fps超えとなっている。ゲームタイトル次第では、十二分に楽しむことができそうだ。
ベンチマークではないが、最後に『鳴潮』をグラフィックス「極低」、解像度1920×1080ドットでプレイしてみた。

©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
背景の描画負荷が高まるシーンでは40fps台に落ち込むこともあるが、30~60fpsを維持していた。シーンなどにもよるが、息抜きにスマホ系ゲームを遊ぶにはありだろう。
シーンは選ぶが魅力十分のパフォーマンスに不足なし
「NUC 14 Pro+」はCore Ultra 9搭載だけあって、手の平サイズながら高い実力を示した。ビジネスワークに留まらず、軽い写真・動画の編集もストレスなく行える1台となっている。一般的にはベアボーンキットとして売られているので、好みのSSDやメモリ容量で組めるのも、うれしいポイントだろう。
しかしながら、写真編集など高ワークロードの処理実行中は、どうしてもファンの動作音(スタンダードモード)が気になる。この辺はパフォーマンスとトレードオフなので、やむを得ないところだ。静音性を重視するなら、消費電力が抑えられているCore Ultra 5搭載モデル(実売9万5000円前後)などを用意している「NUC 14 Pro」シリーズを選ぶ方が、コスパ的にも良いかもしれない。
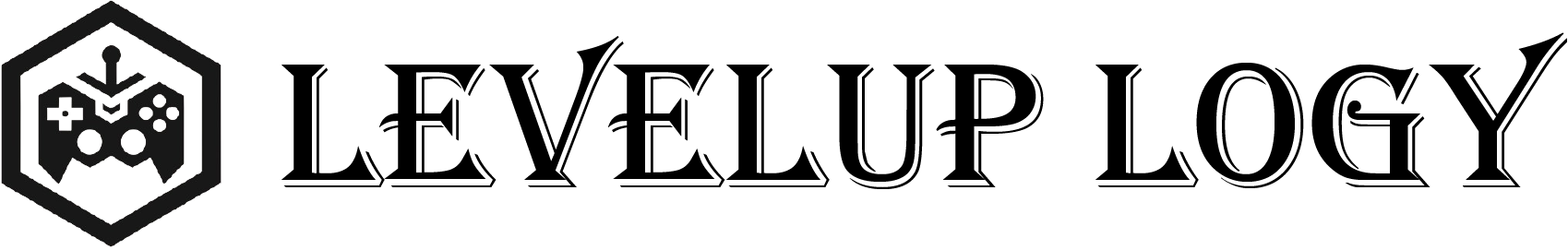




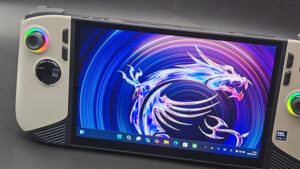










コメント